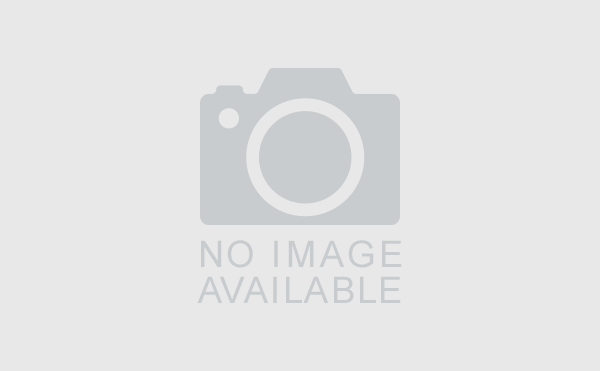技術専門校の指導員の中皮腫・公務認定裁判 弁護団の最終意見陳述書
技術専門校の指導員の中皮腫・公務認定裁判の判決日が2024年11月21日に決まりました。これは、県立の技術専門校の電気工事科の指導員に発症した胸膜中皮腫が公務外認定され、その取り消しを求める訴訟です。
2015年5月に地方公務員災害補償認定請求を行いましたが2017年1月に公務外決定となり、審査請求と再審査請求も棄却され、2020年4月に東京地方裁判所に提訴しました。代理人として神奈川総合法律事務所の福田弁護士と山岡弁護士が就かれ、アスベストセンターの永倉事務局長も支援に入り、中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会の皆さまの応援を頂きながら闘ってきました。原告本人尋問と同僚の証人尋問を経て2024年7月に結審し、11月21日の判決を迎えます。傍聴ご参加お願い致します。本号では、弁護士2人の最終意見陳述書を掲載します。【鈴木江郎】
原告代理人の福田護弁護士
本件の終結に当たって、原告代理人から、総括的な意見を述べます。
1 中皮腫は基本的に石綿ばく露に起因すること
まず最初に、故A氏が罹患し、死亡した中皮腫(胸膜中皮腫)という疾病は、国内外の科学的研究結果としても、また国内の裁判例においても、そのほとんどが石綿のばく露に起因するものであるとの知見が確立していること、逆に言えば中皮腫の発症自体から石綿ばく露が推認されることを強調しておきたいと思います。
ヘルシンキ・レポート(甲11)も「中皮腫の大多数は石綿ばく露によるものである」とし、最高裁でも維持された地裁・高裁判決(甲41)でも、中皮腫発症のほとんどの原因が石綿ばく露であり、短期間・低濃度のばく露でも中皮腫を惹起するとされていることからすれば、石綿へのばく露があってその後中皮腫に罹患した場合、特段の事情がない限り因果関係が認められるとされています。中皮腫の発症にはアスベスト粉じんへのわずかなばく露(数週間)でも十分であるとの、近時の欧州での研究発表もあります(甲47)。
本件審理を通じて、故A氏が1973年4月から1981年3月の8年間、技術専門学校の電気工事科での勤務中、石綿にばく露される作業に従事したことが明らかになっており、A氏の中皮腫は公務に起因するものと認定・判断されなければなりません。
2 技術専門校の校内での石綿ばく露について
故A氏が電気工事科の指導員として勤務していた当時からすでに半世紀が経過していますが、当時の勤務実態は、本件で同僚の証言が得られたこと等により、相当程度明らかになりました。温厚実直で、仕事に打ち込んでいたA氏が、発症してから急速に病状が悪化し、若くして妻子を残して命を失った無念さも、中皮腫という疾患の恐ろしさとともに、伝わってまいりました。
その職場の校舎にも、石綿が使用されていました。A氏がホームベースとしていた職員室を含むいくつかの教室の天井にはトムレックスという石綿含有率の高い吹付がなされており、当時の乾式工法は吹付け後表面から粉じんが落下しやすく、しかも腕白盛りの生徒たちによる清掃その他の活動により吹付材が粉じん化していたと考えられます。また、校舎1階から4階の北側廊下の突き当たりにあった倉庫の天井・壁面には石綿吹付けがなされており、A氏らが書類等を出し入れする際に吹付材に接触していたことは十分に推定されます。しかもこれらの吹付材は毒性が極めて強いクロシドライト(青石綿)であったと考えられ、これは短期間のわずかな吸入でも中皮腫等を発症させるに足るものです。
また、電気工事科の校内実習では、電線はもちろん、配電盤、電動機など石綿を使用した材料や機器を取り扱って指導することが少なくなかったと考えられます。とくに電線については、厚労省の石綿による疾病の認定基準でも電線の絶縁材として石綿紙が使用されていることが明記されていますし、1982年当時、石綿紙・石綿糸が全国の石綿の用途別使用量の相当部分(約5%)を占めていました。なかでも火災報知器等に接続する耐火電線、耐熱電線には石綿含有被覆材が使用されていた可能性は高いと思われます。そして、多くの種類の電線について多様な接続方法を生徒に習得させる過程で、電線の切断、被覆のはぎとり作業が繰り返されますから、指導員もこれら作業によって石綿材料に触れ、粉じんを吸い込むことは不可避であったと考えられます。
このようにA氏は、技術専門校の校内において、日常的に石綿吹付けのある職員室・教室等で勤務し、あるいはA氏が大学病院に入院した際、医師に対し、「配線工の講義をしており、取り扱う材料の中にアスベストが含まれて」いたと伝えたとおり、その校内実習においても石綿材料に触れて、石綿にばく露されていたものです。
原告代理人の山岡遥平弁護士
1 校外実習における石綿ばく露
⑴ 校外実習の内容
故Aは、校外実習として、おおむね毎年12月から2月頃、1ヶ月程度、朝から夕方まで7時間の間、指導員が1日付き添って、生徒に対し、躯体工事から中仕上に入った段階の建物において電気工事の現場を実際に見せ、また、配線作業や通線作業の補助を実際に行わせる業務を行っていた。
なお、被告証人は、校外実習に生徒を朝連れて行って教員は1、2時間で学校に戻ってしまうなどという証言をしているが、意識がもうろうとする中でも学校の授業での生徒への声掛けを行ったり、原告証人からもそのまじめな仕事ぶりを評価されている故Aが、命の危険すらある現場に、中学卒業して間もない生徒を置いてくることは考えられず、故Aには妥当しない。
⑵ 校外実習先の建物で石綿建材が使用されていた
故Aの実習先は、元同僚によれば、高等学校、高等学校、中学校、高校柔道場、大学であり、さらに1980年頃の実習において、県立社会福祉村の工事で実習を行っていた。上記実習先の石綿建材使用について記したのが甲49・甲64である。当時の建設現場では当然であるが、全ての現場で吹付を含む石綿建材が多数使用されていた。そして中学校の北館西階段、北館東階段、北館西第1音楽室からは実際にクリソタイルが検出されている他、高校屋上倉庫、階段1階及び5階倉庫、高校の体育館屋体ステージ柱被覆にもクリソタイルが検出されている(甲2・4~6頁)。これら建材が、切断等されることで粉じんとなり、並行作業で電気工事を補助し、もしくは見学していた故Aも石綿粉じんにばく露されることとなったのである。
⑶ 故Aが実習先で石綿粉じんにばく露されていた
建設現場では一般的に、効率的に業務を行うため各段階の作業が並行して行われることとなる。故Aが校外実習で行っていたのは、主に躯体工事段階や、躯体が出来た後の配線を行う段階であり、この後に、壁や天井を貼るような内装作業が行われる(甲68参照)が、こうした内装作業は、電気工事と並行して行われる。同僚のB証人も、現場では電気のこぎりを使って壁材や天井材を切断したり、溶接を行ったりしている様子を目撃していたし、A証人も、並行して同じ現場で内装材の切断が行われることや、内装材の貼り付けの前に吹付が行われると述べている。こうした並行作業の実態は甲41~43の判決でも認定されている通りである。
そして、元生徒のD氏が「当時の現場はとても埃っぽかった」と述べ、B証人も「すごいもうもうたる粉じんが飛んでいたことは確か」、「本当にほこりっぽいなという感覚」と述べる粉じん状況の中、故A在籍時には危険性に関する認識や対策が乏しく、マスク着用もなく、故Aは石綿粉じんにさらされたのである。
2 故Aの中皮腫は公務によるものである
仮に、被告証言を採用したとしても、建設現場において校外実習をしていた時間は、1日2~4時間程度×20日/年×8年間の360ないし720時間程度はあったというのであり、1日10分×15~20回/年に9年間ばく露したという甲76の事案と比較しても、石綿粉じんにばく露される度合いは高かったものであって、故Aは、認定基準第1の2⑺【建物の補修に係る部分】ないし、同⑾【間接ばく露】にあたる業務に公務上従事しており、その期間は8年間と認定基準の1年を超え、さらに、発症まで最初のばく露から10年を超えているから、認定基準を満たす。
被告審査会は、「被災職員が本件公務に従事していた時間や頻度、被災職員が本件公務に従事した際の実際の勤務環境下での石綿粉じん等の飛散状況が明らかではな」いとして、公務外であるとした。これらの点についても、本件訴訟を通じて、故Aの粉じんばく露の状況は明らかになった。
したがって、もはやその裁決書(甲4の1、31頁)で指摘される、公務外とすべき理由は何らなくなっており、故Aは石綿ばく露作業に従事していたといわなければならないし、公務の他にばく露の機会がなかったことから、故Aの中皮腫発生には公務起因性があり、これを否定した処分は違法であって、取り消されなければならない。
*甲号証は省略しました。