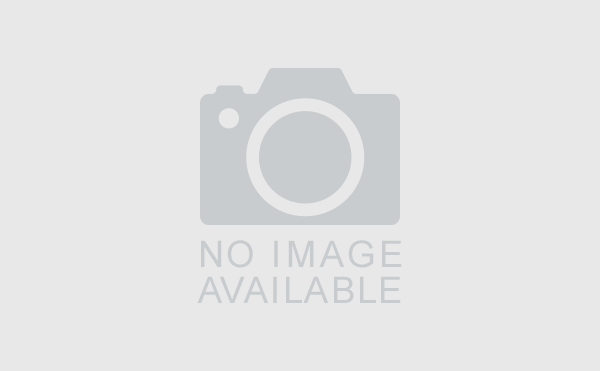技術専門校の指導員のアスベスト公務災害を認定、東京高裁で勝訴!
問題山積みの地方公務員災害補償基金
山梨県立甲府技能専門学校の電気工事科の指導員だった夫の死因である胸膜中皮腫は公務が原因であるとして、妻が2015年4月に地方公務員災害補償基金(基金)に公務災害認定請求をしたが、公務外となった。審査請求、再審査請求いずれも棄却された。妻は公務員のアスベスト被害の広がりを社会に喚起していくこと、基金の認定審査の問題点を明らかにするために裁判での闘いを決意。神奈川総合法律事務所の福田護弁護士と山岡遥平弁護士が代理人となり、2020年4月に東京地裁に提訴するも2024年11月に棄却判決。当然納得するものでないので東京高裁に控訴したところ、1回結審で2025年5月に逆転勝利の判決を勝ち取った。原告の諦めない気持ちと静かな闘志、膨大な建設工事資料を分析し報告書を作成したアスベストセンターの永倉さん、裁判傍聴支援など原告を励まし続けた中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会の仲間たち、そして見事な勝利判決に導いた頼もしい弁護団、皆で勝ち取った勝利である。 【鈴木江郎】
建設現場で実習授業
原告の夫は甲府技能専門学校の電気工事科の指導員で、電気理論・配電図および製図などの「専門学科」、器工具使用法・電気工事基本作業などの「基本実技」、そして「応用実技」の授業を担当していた。「応用実技」の授業では、生徒を連れて近隣の高等学校や大学病院などの公共施設等の建設現場に出向き、実際の工事現場の中で校外実習を行う。具体的には、甲府東高校・甲府西中学校・甲府西高校・甲府第1高校柔道場・韮崎福祉村・山梨医科大学・南アルプス市のアパート・田富町の流通団地などの建設現場で実習を行っていた。
学校の卒業アルバムの授業風景の写真は、まさしく工事現場における電気工事そのものの様子を写している。なかでも「応用実技」の授業風景で、建築現場における天井等への電気配線工事の写真をみると、実際の建設工事における電気配線作業の中にいたことが良くわかる。
石綿ばく露の公務内容
夫は1973年から1981年までの8年間、電気工事科の「応用実技」の授業において、実際の電気工事従事者が建築現場で石綿にばく露するのと同じ状況が生じていた。つまり、「応用実技」として生徒を引率した工事現場の吹き付け石綿の飛散によるばく露や、電気工事と同時並行で行っていた大工等による石綿含有建材の切断に伴う石綿粉じんの間接ばく露が生じていた。これは書類上の裏付けもあり、「応用実技」の校外実習を行った各種工事設計図書や石綿除去工事記録には吹き付け石綿が施工されていたこと、様々な箇所に石綿含有建材が使用されていた事が記載されている。
さらに主治医のカルテには、本人の供述として、『配線工の講義をしており、取り扱う材料の中にアスベストが含まれており、また、実習にて工事中建築物の中に居ることも多かった。(その中には、断熱材等アスベスト含有)』との問診記録がある。つまり本人も公務においてアスベスト建材を扱っていたことを明確に意識し、覚えていたのである。
東京高裁で逆転勝訴!
しかし、基金は公務外と認定。理由として、①潜伏期間が14年と非常に短い、②濃度の濃い状態で石綿を大量に吸ったとは考えにくい、③実習先の建物の吹付石綿除去工事の石綿濃度測定は管理濃度の基準値を下回っている、とした。しかし、この理由はいずれも的外れで、労災認定基準には無い、独自のもので、『石綿による疾病の公務災害の認定については、労災認定基準に準じて判断する』とした基金の内部通知にすら反している。まったくもって不当な決定であり、東京地裁に提訴したが、ここでも基金の判断を上書きするだけの不当判決。深く失望したが、東京高裁の控訴審で、見事に逆転勝訴を勝ち取ったのである。
高裁判決では、地裁判決の認定事実をほとんどそのまま用いながら地裁判決とは逆に、「校外実習先の建築工事現場において校外実習が行われた場所と建材の切断等の作業の場所との位置関係、建材の切断等の作業の時間や方法、切断等がされた建材の量、含まれる石綿の種類などが具体的に明らかでないことや、証人が校外実習先の工事現場で飛散していた粉じんに石綿粉じんが合まれているかは分からない旨供述していることは、当時におけるこの種の事情の詳細が時間の経過等によって現時点において不明となることが特に不審でない」とした。被災者の校外実習先の建設現場における石綿ばく露を認める、常識に則った正当な判決である。そして基金は上告せず、この高裁判決を受け入れた。
公務災害と労災保険の顕著な認定格差
基金が公開している「石綿関連疾患に係る公務災害の申請・認定件数」によれば、2005年度~2023年度の累計で中皮腫では52%、石綿関連疾患全体では44%しか公務上認定されていない。一方、厚生労働省が公開している「石綿による疾病別請求・決定状況」によれば、2019年度~2023年度の累計で中皮腫では96%、石綿関連疾患全体で(石綿肺は除く)94%が労災認定されている。
基金の石綿関連疾患に係る認定基準は労災保険の認定基準に準ずる取り扱いになっているにも関わらず、上記のとおり約2倍もの認定格差が生じている。この認定格差の原因は、基金が遅発性疾患である石綿関連疾患の特殊性(石綿ばく露から発症までの期間が長期間)を考慮せず、請求人に対して過度な立証を負わせている事による。
独自の意見に拘泥する基金の石綿専門医
特に問題なのが、基金の石綿専門医である。高裁判決では、労災認定基準やそれを策定した検討会の議論を踏まえながら、基金の専門医の独自の意見で退けている。基金専門医は労災認定基準やそれを策定した検討会の議論を超えた、恣意的な自らの意見を述べて、なおかつ基金としても専門医の誤った意見を修正できず、そのまま不認定に繋げているのである。
当センターには、公務上石綿ばく露したにも関わらず、公務災害として認められなかった患者や家族から多くの相談が寄せられている。そして、それは上記のような基金の認定実務の問題である。基金は、本判決を踏まえ、これまでの認定実務を早急に見直し、労災保険との格差が生じないように運用を改めるべきである。