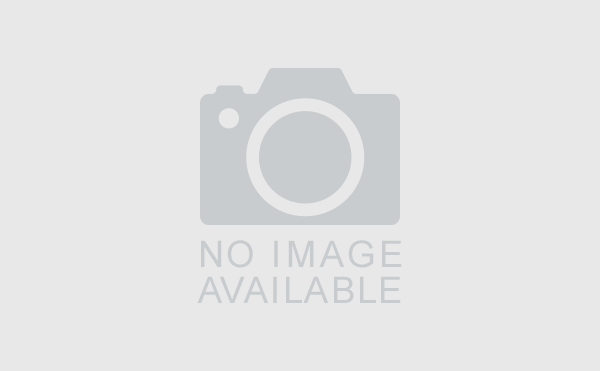メンタル労災、ハラスメント問題:厚生労働省本省と交渉
全国安全センター メンタルヘルス・ハラスメント対策局
5月27日に全国安全センターメンタルヘルス・ハラスメント対策局が、厚生労働省本省に要請、交渉を行った。要望書と文書回答(ごく一部のみ)は省略。やりとりしたいくつかの論点について解説する。【川本】
目次
なぜ精神障害の障害補償の実態を明らかにしないのか?
労災保険法上の症状固定(これ以上治療してもあまり変わらない)になった場合、障害補償を請求できる。ところが、厚生労働省は一貫して、その数字や等級を明らかにしない。しかもその理由が、今回も「システムの仕様上・・・集計を行っておりません」というもの。
業務上外の支給・不支給決定については、件数はもちろん、業種や原因、各局別の数まで発表するのになぜか? 実際、まだ治療が必要で改善の余地のある被災者が一方的に打ち切られている。そして、障害等級も低すぎる。それらが明らかになることを厚労省が恐れているだけなのではないか。
セクハラの心理的負荷は、なぜ「中」なのか?
精神障害の認定基準が改正され、ハラスメントが一つの類型として評価されるようになった。その心理的負荷は原則、「強」。ところが、以前から類型化されているセクシュアルハラスメントは「中」のまま。2年前の専門検討会でも議論したというが、セクハラそのもの評価や企業としての対応など、社会情勢は大きく動いている。直ちに改正するべきである。
労災手続きを嫌がる精神科医や医療機関があまりにも多い!
要求書にあるような診療拒否が理由で、労災請求を断念する被災者が後を絶たない。そのことについて、厚生労働省は、被災者支援ないし労災隠しを許さないといった観点で何とかしようという姿勢は皆無である。課題としても認識していないのが実状だ。
なぜ、ストレスチェックの集団分析を義務化しないのか?
50人未満の事業所にもストレスチェックが義務化されるが、集団分析は努力義務のままである。全国安全センターは法施行当初から、職場改善のための集団分析を義務付けなければ現行の年一回のストレスチェックは意味がないと主張してきた。
厚労省は、集団分析の結果に基づき職場をどう改善すべきか、職場が多様なので難しいなど意味不明の回答。安全衛生委員会で議論すればよいのではないかと提案したが、かみ合った回答は得られなかった。化学物質ですら法律で一律禁止にするのではなく、職場でリスク評価し対策を講じる時代である。法律だけ守っていればよいという感覚では、ストレス職場の改善などできるはずがない。