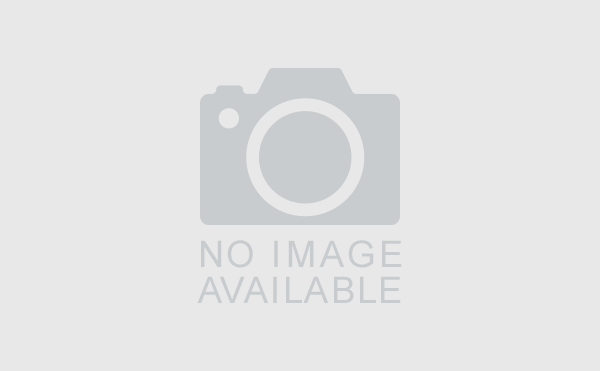「労災保険制度の在り方に関する研究会」に申入れ
厚生労働省が「労災保険制度の現代的課題を包括的に検討することを目的に、労災保険制度の在り方に関する研究会を設置」して、昨年末から議論が始まっています。月1程度開催され、6~7月に中間報告を取りまとめることになっています。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46695.html
下記の内容で、全国労働安全衛生センターが3月5日付で申し入れを行いました。思い起こせば、労働基準法研究会(災害補償関係)が、「休業補償を一律1年半で打ち切る」などの中間報告を突如発表したのが1988年8月のことでした。心ある労働組合と被災者団体が結集して反撃しました。同研究会の委員の大学を訪問し、ある委員とは4回(計7時間以上)にわたって公開討論を行いました。その結果彼は、「中間報告は不十分であり再検討を要する」という申し入れを労働省(当時)に行ったのです。少しでも中間報告がよりよい内容となるように、積極的な働きかけが必要です。 【川本】
制度の在り方
1 傷病補償年金について
労働基準監督署長が職権により給付決定を行うという現行の取り扱いでは不十分であり、被災労働者の請求に基づいて給付が行われるにするべきです。多くを占める脊髄損傷、じん肺、アスベスト関連疾患において、各労働局、労働基準監督署での取り扱いの大きな違いもみられます。
2 時効について
少なくとも民法に準じて早急に2年を5年に改正するとともに、とりわけ遅発性疾病についての時効の取り扱いを廃止するとも検討されるべきです。
3 通勤災害保護制度について
職住接近の労働者は極めて限られていること、テレワークが増えたことなどを踏まえて、現行の通勤災害保護制度を廃止して、労災補償制度に組み込むべきです。
4 打切補償制度について
事実上ほとんど適用されておらず、障がい者雇用も推進されてきたことなどを踏まえて、打切補償制度に関する労働基準法(第81条)及び労災保険法(第19条)の規定は廃止すべきです。
5 男女の遺族補償制度について
女性は20代前半までに結婚して「退職するのが当然」であった労働基準法制定当時との最大の変化ではないでしょうか。また、本研究会のような厚労省の専門家会合の過半数が女性であることは隔世の感があります。本研究会と同じぐらいに総論的な議論があったと思われる、1988年8月に中間報告を発表した「労働基準法研究会(災害補償関係)」の構成員は、弁護士の若菜允子氏以外全員男性の法学部教授(1名は助教授)でした。共働きが当たり前、ジェンダー平等の時代、性別、性自認に関わらず実態に応じて、遺族補償年金を受給できるようにするべきです。
6 不服審査制度について
現行の不服審査制度を廃止して、労働委員会と同様の制度にすべきです。
7 労災指定医療機関制度について
精神科クリニックが増える中で、労災患者は労災指定医療機関が診るものという誤解がかなりの割合で存在しています。精神科学会などに直接働きかけて、指定医療機関の拡大と、指定を取らなくても労災保険請求できることを啓発してください。
8 健康保険の傷病手当金制度について
とりわけ業務上疾病の場合、健保組合によっては労災請求するならば傷病手当金を出さない、保留とする、けんぽ協会でも会社が手続きに協力しないケースが多く見受けられます。事実上の労災隠しの温床になっているので、後で清算することを前提に、とりあえず両方を請求できるようにもっと周知してください。
適用や徴収
1 メリット制について(14~15頁「別紙」参照)
2 暫定任意適用事業について
暫定任意適用事業を廃止して、労災保険を全事業に適用すべきです。
3 労働者性について
一口に、個人事業主、フリーランスと言っても、業種や職種によって、発注者との関係はさまざまです。必然的に労働者性の判断基準そのものも大きく異ならざるを得ません。フリーランス保険を作ったことは評価できますが、むしろその加入者に労働者が紛れ込んでいないかどうかのチェックをきちんと行う仕組みを作ることが強く求められています。いかなる受注関係であっても、「特別加入しないと現場に入れない」建設業界の実態を見れば明らかです。
給付内容の改善
1 休業補償水準を100%に
休業特別支給金を給付に組み入れることを含め給付水準を100%に引き上げることを検討すべきです。治療に専念することは元気に働くための準備作業です。休業補償受給中の被災者は、キャリアアップも副業もできないのです。あわせて休業当初の3日間の休業補償も給付するようにするべきです。請求書面上のチェック機能で休業4日未満の休業災害の死傷病報告書の未提出も解消されるはずです。
2 障害補償の水準引き上げ
障害補償年金の対象となる障害等級を10級程度にまで拡大することを検討すべきです。障害者の法定雇用率が引き上げられてきたとはいえ、納付金で対応する企業も少なくなく、その労働条件は極めて低水準にとどまっています。労働能力を2~3割も失った被災者が、被災前の労働条件を維持できる企業は限られています。一時金にせよ年金にせよ給付水準全体の引き上げも検討するべきです。
3 介護補償給付について
親族等による無料介護も給付対象としつつ、上限額を廃止して、実際に介護に必要な額が給付されるようにするべきです。また、介護補償給付を受給している障害補償年金受給者が、療養が必要になった場合に、介護補償給付の受給権を失うことなく療養補償給付も受給することができるようにするか、または傷病補償年金に移行して介護補償給付と療養補償給付の双方を受給することができるようにするか、いずれにしろ時期を失することなく(手続的に迅速であることが重要です)、療養補償給付で必要な療養が受けられるようにする措置を講じる必要があります。
4 平均賃金の算定方法について
アスベスト疾患のように潜伏期間が長かったり、発症原因のばく露時期の特定が困難な場合は、生活保障の観点からの調整が必要です。少なくとも、若いときにばく露したために、休業補償が傷病手当金よりも低額になることのないようにするべきです。明らかにアスベスト労災隠しにつながっています。
5 休業補償の最高・最低限度額について
厚生年金の障害年金が給付される1年半が経過した段階で、平均値、せめて中間値まで最低限度額を引き上げるべきです。
6 特別加入者における「全部労働不能」の取り扱い
特別加入者の休業補償支給の要件に「全部労働不能」があります。最近、この要件に基づいて休業補償が支給されなかったアスベスト被災者の事案では、軽微な労働も難しい状態でしたが、「電話等はできる」という理由でした。審査請求、再審査請求も棄却されました。その判断の根拠となる通達は昭和40年(1965年)に出されたものです。つまり、60年前の建設業者の状況を前提にしたものです。このような時代錯誤の不当な取り扱いは廃止すべきです。
労災補償の認定をめぐって
1 新型コロナワクチン接種の業務遂行性について
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合の労災保険給付について、医療従事者等および高齢者施設等の従事者のワクチン接種は業務行為として労災保険給付の対象となっています。一方でその他の業種の労働者は、事業主からの業務命令性を調査した上で個別に判断するとされています。現実に医療機関で働いていた医療事務の公務員に対して、「事務職」という理由でワクチン接種の公務遂行性を認めなかった事例が発生していますしかし、新型コロナワクチン接種は政府、自治体、報道などあらゆる機会で接種が推奨されてきたもので、事業所からも明示的もしくは黙示的な接種圧力がありました。上記以外の労働者についても業務起因性を幅広く認め、ワクチン接種は業務行為として労災保険給付の対象とするべきです。
2 腰痛・上肢障害等について
とりわけ腰痛症については1975年から認定基準が変わっていません。例えばMRIなど使われていません。50年前の検査方法、医学水準によって、業務上外、症状固定等の判断を余儀なくされている監督署職員や労災医員は大変苦労されています。新たな疾病はもちろんのこと、これまでに業務上疾病として認定されてきた疾病の最新の医学情報を漏れなく各都道府県労働局へ通達するべきです。腰痛多発職場や作業態様の変遷を受けて、予防対策のガイドラインが作られていますが、労働基準監督官の安全衛生指導業務に、労災保険担当職員は一切関与していません。ガイドライン等で触れられている内容を労災保険業務担当職員や労災医員に周知するべきです。
3 労災補償をめぐる労働時間の事実認定について
賃金未払いで事実認定される労働時間と、労災保険手続きの中で事実認定される労働時間は、本来であれば同一であるはずなのですが、タイムカードで労働時間管理された工場労働でない限り事後的に労働基準監督署が事実認定することがますます難しくなっています。一方で、労働時間規制の強化に伴い、労働基準監督官が事実認定する労働時間しか、労災保険給付調査においても認めようとしないのが現状です。
労災保険手続きでは、かつては「本人の手帳のメモ」や、自宅への「帰るコール」のようなものでも、比較的緩やかに労働時間として認められていました。ところが、現在は、会社が管理する客観的な労働時間記録や明らかに時間を要することが明白な成果物などがなければ、労働時間として認められていません。場合によっては刑事罰を科す厳密性を有し、司法警察権をも行使して把握する労働時間と、遺族請求も含む労災保険請求手続きの調査における労働時間が全く同じものにはなりません。結果として、労働時間が過小評価されて不支給となる事例が多数みられます。
4 脊髄損傷やじん肺患者の遺族補償について
長期間にわたって療養している脊髄損傷やじん肺患者が亡くなられた際に、死亡診断書の病名が別疾病であることから遺族補償請求が業務外となることが少なくありません。明らかに当該疾病とは関係のないことが明白な場合以外は、全て遺族補償の対象とすべきです。脊髄損傷患者の、「あの時死んでおけばよかった」などという嘆きを聞きたくありません。
5 精神疾患の症状固定について
労働基準法制定当時はおろか、21世紀になるまで非器質性の精神障害の労災患者は皆無でした。もちろん主治医意見の尊重が原則ですが、信頼できる主治医に出会えない場合も少なくない上に、「労災申請するなら転院してください」と言われることが非常に多いのが現状です。そして、薬物が功を奏する個人差やおかれている環境によって、医学的に症状固定の判断が極めて困難です。10年が珍しくなく、20年以上の被災者もいます。職場や社会復帰についての福祉制度の活用も含めて、休業補償と療養補償を丁寧に整理して給付管理することは一つの改善策です。
労使関係その他
1 事業主の申請手続きへの協力について
業務上疾病の場合、協力的ではない会社に依頼すること自体が労働者にとっては苦痛であり、無意味です。また、会社の協力がなければ請求できないと考える労働者ならびに医療機関(ほぼ全て)が多いのも現状です。休業災害であれば死傷病報告書の提出が義務付けられていますし、業務上疾病については、あくまでも本人請求を原則として、会社の証明欄を任意にするべきです。
2 労働基準法19条などについて
通勤災害が給付対象となり、全ての法人が加入対象となった健康保険の傷病手当金と休業補償給付の差も小さくなってきた中で、労災と通勤災害ないし私傷病との、雇用に関する大きな違いは、休業期間中の解雇が認められているかどうかです。会社の過失がなくても労災の解雇制限がある一方で、むしろ本人過失が全くない通勤災害や業務起因性が疑われる私傷病も少なくないことから、通勤災害や私傷病についても労働基準法ないし労働契約法を改正して解雇制限を設けるべきです。
3 監督官と労災保険事務官との連携について
Dの3とも関連しますが、行政改革のあおりで、10年以上にわたって労災保険事務官の新規採用がありませんでした。その頃、労働基準監督官が労災保険業務を「手伝っていた」労働基準監督署もあるのですが、いわゆる働き方改革推進のため労働基準監督官が本来業務に戻ってしまいました。過労死等の労災保険請求が増え続ける現実を踏まえ、監督官以上に労災保険事務官を増員すべきです。
40年前に多数存在したじん肺や振動病の労災請求の調査は、そのほとんどが医学的なもので、比較的「単純」です。すぐに増員することが難しければ、一時期行われていたように労働基準監督官を労災保険業務に従事させるべきです。労働基準法違反の申告処理の多くを占める賃金未払いと同じように、労災補償をしないことは労働基準法違反のはずです。精神疾患の原因が、ハラスメントや退職勧奨など、個別労使紛争に関与したことのある監督官でなければ、その心理的負荷が評価できないこともあります。
4 社会保険労務士の在り方について
労働者にとっては不要で、労働者や労働組合に敵対する、労働基準監督署の是正勧告も必ずしも従わなくてもよい、などと指南する人がいるので、労働基準監督署の看板だけは、とにかくやめてください。
メリット制の廃止について
今回の研究会においては、労災保険制度の「徴収」の領域に関する検討として、メリット制が議論の俎上に挙がっており、第一回の会合でも複数の委員から、メリット制に関する発言が行われている。メリット制については、少なくとも下記の3点のように重大な問題があり、見直しではなく、その廃止を視野に入れた議論・検討が行われるべきである。
(1)メリット制についてはこれまで、厚労省などが「労災防止努力の一層の促進に効果がある」と主張してきた。しかし、実際には労災防止効果のデータが示されたことはない。厚労省の過去の専門家検討会においても、「労災防止効果のデータがない」「労災防止効果が上がるのか」と繰り返し疑問の声が上がってきた 。そして、「メリット制が労災隠しを助長する」との指摘が、日本医師会や労働組合などから示されてきた経緯がある 。つまり、メリット制には、労災防止のインセンティブがあるかどうか極めて疑わしい一方で、労災隠しを助長する負のインセンティブが存在するのである。
(2)メリット制については、「保険料負担の公平性の確保」ということが言われてきた。しかし、2020年12月7日に『第2回労災保険財政検討会』で配布された資料 によれば、メリット制の適用を受ける大企業が保険料の割引を受けやすく、メリット制の適用を受けない小規模零細の事業主の保険料負担が重くなる、いびつな保険料計算が行われている。メリット制の適用を受けず、割引分を負担させられている95%の事業主にとって、メリット制に「公平性」はない。
(3)国際的にも、メリット制のような仕組みについて、労災事故を減少させる効果を示すような証拠はないとされており、逆に「使用者に労災申請を妨害し労災被災者を攻撃する動機を与える」との指摘がされている。例えば、国際労働機関(ILO)は、2011年に発表した文書 の中で、労災保険制度の「経験率」(メリット制を指す)について、「経験率に関してもっともよく聞かれる論拠は、それが使用者に業務上の障害の頻度と重大性を減らすインセンティブを与えるというものだが、そのような効果があるという信頼に足る証拠はない。」と指摘。そして、「経験率は使用者に、請求の提出を妨げまたは抑制し、積極的な情報の差し控え、請求に反対し、請求者に有利な決定に不服を申し立て、請求者に早期の職場復帰を迫り、請求者に関する個人医療情報を求め、請求者にさらなる医学的検査を要求するなどの経済的インセンティブを与える。」と、労災隠しや労災被災者への攻撃など、その負のインセンティブを指摘している。
今回の研究会の第1回会合では、残念ながら上記(1)~(3)の問題に関する議論は、ほとんど行われなかった。特に、メリット制が使用者による労災隠しを助長し、労災被災者への攻撃につながるという問題について、どの委員からも一言の言及すら無いという衝撃的な内容であった。研究会の各委員は、過去のメリット制に関する議論を再確認すると共に、実際の労災被災者の切実な声に応える真摯な議論を行うべきである。
なお、昨年の「あんしん財団事件」に関する最高裁判決や、昨年1月の厚労省の新たな通達 は、「メリット制が労災隠しや労災被災者への攻撃につながる」という負のインセンティブがまさに顕在化した事例である。労災認定後も、その認定内容について使用者が争いを継続する道を開き、労災被災者の療養や職場復帰を困難にする状況を、メリット制が助長しているのである。今や、メリット制の負のインセンティブについての議論が必要不可欠な状況になっていることは明らかである。
全国労働安全衛生センター連絡会議は、今後の「労災保険制度の在り方に関する研究会」において、上記(1)~(3)に挙げたメリット制の問題を正面から議論するよう、強く要望するものである。そして、メリット制の廃止を含めた踏み込んだ議論を行うよう求めるものである。
厚労省の過去の専門家検討会で出された議論の一例としては、下記の通り。
2004年6月14日の『第3回 労災保険料率の設定に関する検討会』では、岩村正彦座長(東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授)が労災防止効果について、「問題は、その点についてのきちんとしたデータ的な検証があるのかどうかということなのです。」「アンケート調査以上に、いままで何か試みたということはあるのでしょうか。」と発言。それに対して厚労省の担当者が「私が記憶するところでは、していないと思います。」と回答している。
また、2004年9月8日の『第6回 労災保険料率の設定に関する検討会』では、大沢真理委員(東京大学社会科学研究所教授)が「(メリット制の)増減幅を拡大すれば、インセンティブは促進されるかもしれないけれども、インセンティブが促進されたからと言って、災害防止のための人的・時間的・金銭的な投資が実際に増えるのかどうか。」「メリット制の増減幅を拡大したら必ず労災防止効果が上がるのかという辺りは、実は検証されていません。」と発言。
2011年1月19日の『第3回 労災保険財政検討会』では、山田篤裕委員(慶應義塾大学経済学部准教授)が「果たして、きちんとメリット制の本来の目的である労災を減少させることに寄与するのかというのが言えない」と発言。
メリット制が労災隠しを招くという「負のインセンティブ」について、過去の専門家検討会での議論や、関連団体からの懸念の声などは、下記の通り。
2004年6月14日の『第3回労災保険料率の設定に関する検討会』では、岩村正彦座長が「下手をするとうまく立ち回って災害を隠してしまおうというインセンティブにもなってしまうのです。その辺はいままでに実情を調査されたことはありますか。」と発言。それに対して厚労省の担当者が「労災隠しの問題については、統計は特にとってはいません。」と回答している。
また、2010年12月7日の『第2回労災保険財政検討会』では、小規模事業場へのメリット制拡大が議論された際、山田篤裕委員から「小規模事業場だと…(略)…労働者数が少ないことから、労使関係いかんによっては労災隠しのインセンティブに気をつけなければいけない。」と発言した。
さらに、日本医師会の労災・自賠責委員会の答申(平成28年2月)では、「事業者による『労災かくし』を助長し、一向に排除とならない原因の一つとしてメリット制が挙げられる。」「本来は災害防止努力を促すためのメリット制が、労働災害が発生すると保険料負担が増えるという認識を事業主が持つこととなり、その結果労働災害をかくすという行動につながっていると考えられる。」と指摘している。https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20160323_5.pdf
また、平成17年1月17日の『労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会』では、佐藤正明委員(全建総連書記長)が、労働組合の立場から、「労災かくしの問題とメリット制の問題を切り離して物事を議論するのは、私はなかなか納得できない」と発言。
2020年12月7日『第2回労災保険財政検討会』の配布資料。「継続事業 メリット増減率+0%・▲40%の賃金総額規模構成比」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/3-11rousaizaisei.pdf
ILO労働安全衛生エンサイクロペディア(2011.2.23)の記述 https://joshrc.net/archives/13875
厚労省の新たな通達は、メリット制に基づく労災保険料の値上げに対して、事業主が労災認定の内容に対する不服申し立てを行うことを可能にし、労災認定の内容を否定する判決が出た場合に労災保険料の値上げを取り消す対応を取る、との内容。事業主に労災の事実を否定する新たな武器を与え、被災労働者の療養と権利を脅かす深刻な問題である。