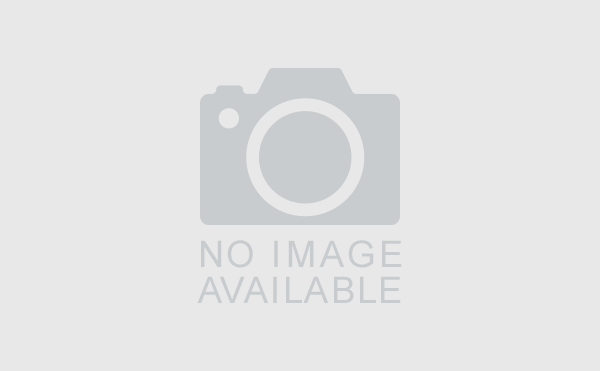メンタル労災ほっとライン」の取り組みとハラスメント対策:西山和宏(ひょうご労働安全衛生センター事務局長)
目次
はじめに
今年も、10月10日の世界メンタルヘルスデーに合わせて「メンタル労災・全国一斉ほっとライン」を実施した。主催は全国労働安全衛生センター連絡会議メンタルヘルス・ハラスメント対策局で、コミュニティ・ユニオン全国ネットワークに加盟する地域ユニオンの皆さんにも協力をいただいた。
10月11日㈮と12日㈯の2日間を中心に、全国12ヶ所(札幌・東京・山梨・神奈川・名古屋・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・徳島・福岡)に相談ポイントを設けた。
寄せられた相談件数は全国で217件(昨年は9ヶ所217件、一昨年は11ヶ所97件)であった。
フリーダイヤルを活用
全国センターは、相談対応用にフリーダイヤル(0120-631-202)を開設している。昨年初めてこのフリーダイヤルを活用してホットラインを開設したところ例年以上の反応があり、今年もフリーダイヤルの番号をマスコミに周知し、取り組むことにした。
ホットライン開設に向けて厚生労働省の記者クラブで会見を行い、各地でもマスコミへの周知が行なわれた。全国紙の地方版や地方紙、テレビやラジオでも取り組みが紹介された。そしてホットライン初日、このフリーダイヤルの番号が昼のニュース全国的に放送され、テレビの放映直後から各地の相談窓口には電話が相次いだ。あらためてマスコミ対策の重要性を痛感した。
相談の傾向
各地の相談ポイント毎に集計したデーターをもとに(現時点で札幌・東京・広島の相談件数52件が未集計)相談傾向をまとめてみた。
性別では、男性が72件、女性が72件であった。
年代別では、29歳以下が6人、30代が10人、40代が16人、50代が37人、60歳以上が29人であった。子どもの健康状態を心配した親からの相談が多かったのも特徴であった。
相談者の雇用形態は、正規社員が60人、非正規社員が20人であった。正規社員からの相談が多い傾向はこの間続いている。非正規職員が増える中で、少数化する正規社員の働き方は肉体的にも精神的にも負担が増大していることが影響しているのではないだろうか。
相談者の職種は様々であったが、多かった職種順でみると、事務的職業23人、福祉・介護の職業13人、製造・修理等の職業11人、配送・運送・運転の職業11人、医療・看護の職業8人、保育・教育の職業8人、販売・営業の職業8人であった。
ハラスメント行為者については、最も多かったのが上司39人で、次が職場のトップ22人(社長9、店長4、園長3、院長3、施設長2、学校長1)であった。職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等のハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が定められている。ハラスメント防止に向けて先頭に立つべき事業場のトップが行為者であった場合、被害者は、職場の改善よりも退職を選択せざるを得ない場合が多くなる。
ハラスメント行為の類型
職場のパワーハラスメントについて、行為内容により類型化されている。それは、①身体的な攻撃(暴行・傷害)、②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)、③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)、④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)、⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)、⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)の6類型である。もちろん、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてを網羅するものではなく、これ以外の行為は問題ないということではない。
今回の相談内容を6つの類型に分類すると、①5件、②72件、③9件、④12件、⑤5件、⑥2件であった。この分類は電話を受けた相談スタッフの判断によるもので、類型に分類できない相談や、複数の類型に該当する相談もあった。
いわゆる「パワハラ防止法」では、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、③労働者の就業環境が害される、3つの要素を全て満たすものをパワーハラスメントと定義している。先ほど相談内容を6類型してみたが、「パワハラ防止法」の定義に該当する事例は多くはなかった。しかし、多くの相談内容は人権を侵害する行為であり、「労働者の就業環境を害する」内容であった。
相談の特徴
今回のホットラインは、「メンタル労災」をテーマに掲げたが、例年以上に労災申請を行なっている、行ないたいという方からの相談多かったのが特徴であった。そして、過労自死案件の相談もあった。「夫が55歳で急性心不全で死亡した。遠方への出張が多く、死亡直前に頭痛を訴え、病院に行ったが翌日死亡」「24年1月から仕事に行けなくなり、うつの診断。本人は復帰を希望していたが、社長は辞めろとばかりの対応。本人は『社長が怖い』と言い、4月に自宅で首吊り自殺をした」。
また、過去の出来事に悩んでいる方からの相談も多く、5年前、10年前の出来事や、一番古いのでは平和3年の出来事があり、ハラスメント被害の深刻さについて考えさせられた。
具体的相談事例から見えてくる職場実態
具体的な相談事例を紹介する。医療機関を受診し、精神障害の診断を受け治療・休職中の方からの相談も多く、現在の職場のギスギスした人間関係が浮かび上がってきた。
〇掲示板前に置いてあったコピー用紙を移動させたら同僚になぐられた。
〇前事務長が突然退職し、総務課長からいきなり事務長になったが、総務課長の仕事がなくなる訳ではなく、単に事務長の仕事が加わっただけなので月45時間以上は当たり前、80時間以上の残業になった。他の職員からも業務について文句や中傷めいた内容の発言や対応をされる状態。今年7月14日にうつ病を発症。
〇元々リサーチ業務担当だったが、会社がリサーチ業務をやめて、キャッシュレス決済事業を行うことになった。それをきっかけに「あなたは何の仕事ができるんだ?」等と言われ、社長自身も犯しているミスなのに、自分がミスしたら強く指摘される等し、計2回基本給も含めて賃下げされた。
〇取締役部長兼店長から、自分だけがトイレを綺麗にしろと言われる。適応障害・うつ病発を発症し、6月に退職した。
〇ばかやろう、殺すぞ、この中卒が、キチガイ、首しめたろか等の怒号が飛び交う職場。こういう人が何人もいる。私は平気だが、言われている人が心配。
〇販売で働く30歳の息子。大卒8年目。上司から無能呼ばわりされ、カバンや時計など私物にケチを付けられる。先日は車中で1時間怒鳴られ続けていたことが録音に残されていた。車で帰宅後、なかなか室内に入ってこないので様子を見に行くと、車中で自分の髪の毛をむしり取っていて、膝の上に毛玉ができていた。
〇建設会社社長の社用車の運転手。休憩なし12日間連続勤務など業務過多でうつ病発症。賃金も支払ってもらえないばかりか車をこすったということで弁償を求めて自宅まで毎日襲撃を受けている。
〇ビル管理会社で働く夫(67歳)が職場で携帯を壊されたり、リュックの持ち手を曲げられたり、ロッカーを壊されたりした。本人は部長に面談で何も言えず、うつになり、5月に退職。
〇生産管理部で不正行為に加担させられた。品質保証課に相談したら改善された。報道されたことにより、「悪いことをした」という意識からメンタル不調に陥って休業中。
〇仕事についての連絡が、私にだけ取り次がれず、皆から無視される。
〇スーパー勤務。男性主任から睨み付けられる。他の従業員が集まっている前で、「ミスが多いからこの子が根付けした物は全員でチェックするように」と言われた。会社の相談窓口にハラスメントとして相談したが、改善されず、処分もなかった。
〇勤務先の修理部門の責任者がきちんと教えてくれない。忙しくて余裕がないのが原因だと思うが、めんどくさがられ、時に怒鳴られる。元の職場の部長に相談すると今の職場責任者を注意した。謝罪されたが余計にこじれ、適応障害と診断された。
〇転職(食品関係)したばかりなのに誰も仕事を教えてくれない。商品の値札づけ等で苦労し、時間外も月60時間位あるが、店長にも相談できない。以前うつ症になったことがあり、今の状況が続くと再発の心配がある。
〇妻からの相談。夫が店長から電卓を投げつけられたり暴言をはかれたり、皆の前で「どんなに頑張っても評価しない」「お前とは仕事しない」と言われ挨拶しても無視される。会社の人事に相談したが何年も放置されている。夫を自主退職させようとしていると推測するが、対処の仕方がわからない。
〇50代後半。人材開発部に4年前に異動。入社間もない若い社員から「こんなことも知らないのか」「こんなこともできないの」と高圧的に言われる。再雇用の年配者4人に対しても言葉遣いが悪く同じような言い方をする。昨年度人事評価を下げられ、昨年から進めてきた企画を一方的に破算にされた。そのことで心が折れ、適応障害と診断され休んでいる。休職前に課長に相談したが、若い子たちに何も注意しない。
ハラスメント相談にどう向き合うのか
現在、行政相談窓口やユニオンに寄せられる相談で一番件数が多いのはハラスメントに関する内容である。この傾向はもう何年も続いている。相談内容は、いじめ・パワハラだけでなく、セクハラやカスハラなど様々なハラスメントに対する相談が増えている。
一方、相談を受けたメンバーからは、「労災認定に繋がらない」「組織化に繋がらない」「1件の相談に時間を要する」「何度も同じ人から相談電話がある」等の声も聞えてくる。
今年10月5日~6日にコミュニティ・ユニオン全国交流集会が大阪で開催されたが、その中で、「ハラスメント相談にどう向き合うのか」をテーマに分科会がもたれた(本誌6頁参照)。
特徴的だったのは、相談から面談へ、そして組織化後の団体交渉において、会社側がハラスメントを認めない事例が多くあるという点であった。「パワハラ防止法」により、3つの要素を全て満たすものをパワーハラスメントと定義されたため、会社側が「パワハラではない」と主張し、解決に時間を要するという報告が多かった。
また、職場の同僚間でのトラブルに関する相談が増えているが、団体交渉において会社側は、社員間の問題だとしてその責任を認めないという報告も特徴的であった。その他、解決までに時間を要し生活保障面で苦労している事例や、医療機関など専門家へのつなぎや相談者(組合員)の体調不調への対応に苦労している報告等があり、経験を交流することができた。
グレーゾーンの対応
パワハラの定義に当てはまらない言動について、企業に責任は無いのか。労働組合として、どの様な対応が求められるのか。
産業精神保健誌の最新号が「パワーハラスメント防止と産業精神保健」を特集しており、「パワーハラスメントの法的理解(グレーゾーンの見きわめ)」と題し、原昌登氏(成蹊大学)の論文も掲載されている。その中でY銀行事件(徳島地判 平成 30・7・9)が紹介されている。概要は以下の通り。
ミスを繰り返す部下Aに対し、上司らから日常的に強い叱責が行われていた。Aは同僚や家族に死にたいと訴えるようになり、同僚は上司に知らせるものの、上司は真剣に受け止めることはなかった。その後、Aは自殺に至り、Aの母親が、自殺の原因はパワハラであるとして、銀行に損害賠償を請求した。
裁判所は、ミスを指摘し改善を求めるのは上司らの業務であり、叱責が続いたのはAが頻繁にミスをしたためで、叱責自体が業務上の指導の範囲を逸脱しているとまでは認められないとして、上司らの言動は不法行為に当たらないとした。しかし、上司らによる叱責はさらに上の上司も認識しており、銀行はAの自殺願望等が上司らとの人間関係に起因することを容易に想定できたから、Aの心身に過度の負担が生じないように対応すべきところ、対応が不十分であったとして、銀行の安全配慮義務違反は肯定した。結論として、慰謝料など総額約6142万円の支払いを銀行に命じた。
さいごに
今回ホットラインに寄せられた相談も、日常的に受ける相談も、「パワハラ防止法」の3要素を全て満たす相談は少ない。しかし、労働者の就業環境が害されているのは事実である。職場環境を害する全ての言動を如何に要求化し、改善に繋げていくのかが求められている。「職場環境が害されている」具体的問題点を積極的に見つけ出し、被害者と同僚らが相談し合い、一緒に問題を考え合い、改善に向けた取り組みを実践することが重要である。この実践こそが求められているのではないだろうか。