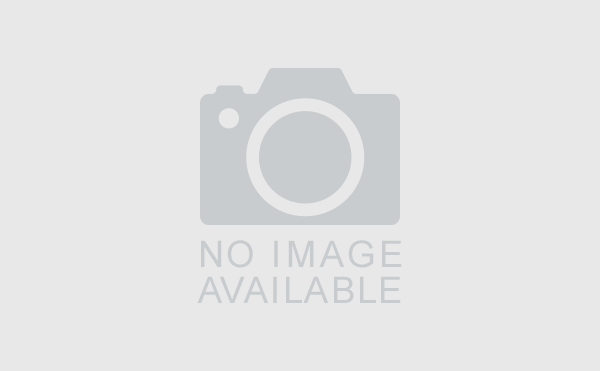コミュニティ・ユニオン全国交流集会 in大阪:ユニオン仲間と、労働安全衛生の課題について学ぶ
10月5~6日、コミュニティ・ユニオン全国交流集会が大阪で開催され、全国各地で活動する一人でも誰でも入れる労働組合の仲間が約420名参加した。労働安全衛生の課題として、今年はハラスメントとセクシュアルハラスメント労災の分科会があった。それぞれの分科会で座長を務めた、西山和宏さん(ひょうご労働安全衛生センター)と、田島陽子さん(関西労働者安全センター)の報告を紹介する。【川本】
ハラスメント相談にどう向き合うのか:西山和宏さん(ひょうご労働安全衛生センター)
最初に、NPO法人ひょうご働く人の相談室の山西伸史さん、よこはまシティユニオンの平田淳子さんのお二人から報告を受けました。山西さんからは、兵庫県下のユニオンが中心となって、労働相談活動を専門とするNPO法人を設立し、増加しているハラスメント相談に対応していることが報告されました。平田さんからは、被災当事者や支援者がお互いの状況や思いや経験を語り合い、励ましあえる場として「被災者交流会」を定期的に開催していることが報告されました。ユニオンとして、相談を受けるチャンネルをいかに増やすのか、そしてハラスメント被災者が「一人ではないんだ」と感じ勇気を得られる場をいかに作り出すのか、その大切さを学び合いました。
その後、経験交流と意見交換を行いました。具体的な取り組みとして、「職場で一人だけ孤立させられ、机を壁に向けて座るように席替えをされ、ユニオンに加入した組合員がいる。団体交渉を行っているが、会社は『パワハラではない』という対応だが、交渉を開始してから上司は異動になった。組合員を孤立させないように、執行委員で担当を決めて連絡を取り合い、常に本人の思いを聞くようにしている」「パワハラ・セクハラ被害を訴えたが、団体交渉で会社は認めない。逆に職場秩序を乱したとして組合員は出勤停止の処分を受けた。パワハラとセクハラに対する慰謝料と未払い残業代の支払いを求め労働審判を行い、和解した」などの報告がありました。
参加者の皆さんには、①相談対応において、②面談、組織化おいて、③団体交渉において、④心のケアにおいて、の4点に絞って苦労している点や工夫している点についての報告を求め、交流しました。団体交渉において会社側がハラスメントを認めない場合の対応、そして解決までに時間を要する場合の対応など、貴重な報告が持ち寄られました。そして、パワーハラスメントの3つの要素を満たしていなくとも、労働者の就業環境が害されている事実について、ユニオンとして如何に要求化し、労働環境を改善することの大切さを学び合いました。分科会の参加者は42名でした。
みんなで考えるセクハラ労働相談:田島陽子さん(関西労働者安全センター)
参加者は13人と座長・発表者合わせて15人でしたが、少人数である分、気楽な雰囲気で行うことができました。
ハラスメントの中でも、セクシュアルハラスメントに絞ると話が狭くなるということもなく、セクハラをきっかけに被災者がさらにセカンドハラスメントや解雇などにあい問題が深刻化かつ増加することが多く、相談対応としても、こころのケアの問題、労働問題での団体交渉、労災補償の請求、損害賠償など多岐にわたった対応が必要となります。事例を紹介して、どのような対応をして、どういう結果を得たのか、参加者と共有しました。報告者の用意した事例以外に、参加者から取り組みの紹介もありました。事例のほとんどは被害者が退職に追い込まれており、男女雇用機会均等法があり、パワハラ防止対策法が施行されても、使用者側の無知や無策によって悪い結果になりがちであると感じました。使用者側がセクシュアルハラスメントを把握したときに、事実関係の調査、問題の適正な評価と判断ができないのです。
支援者やユニオンとしては、早い段階で相談を受けることができれば、問題が深刻化する前に本人を支えたり、介入して、解雇にあったり精神的不調が深刻化する前に対処できるかもしれないとの思いです。よこはまシティユニオンでは、会社に対して団交や抗議行動をするのでなくても、ユニオンに居場所や人とゆるいつながりを持ってもらえるような場を作ろうと試みているそうです。
反省点としては、事例を持っておられない参加者が遠慮してかほとんど発言いただけなかったので、もっと主催者側で、他の人も話してもらえる工夫をすればよかったと思います。