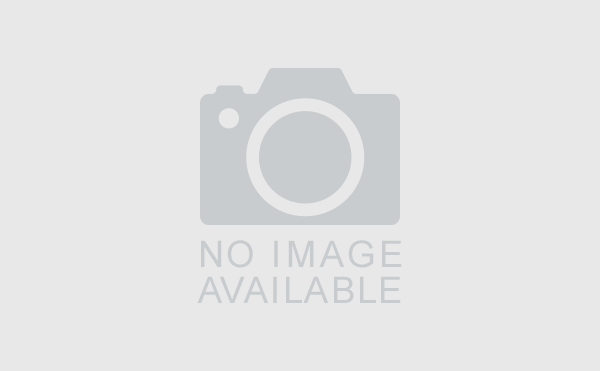労災事件ファイル:港湾荷役とフォークリフト運転業務 非災害性腰痛で労災認定
目次
後ろ向き運転と凸凹道の振動で、腰部に過度な負荷
数年ぶりに港町診療所に港湾荷役労働者の腰痛労災の相談がありました。18歳頃から52歳頃まで港湾荷役の重量物を取り扱う重筋肉労働に従事しながら、31歳頃から65歳までフォークリフトの運転業務も行っており、その両方の業務により変形性腰椎症を発症されました。ご本人から長年の作業でいかに腰部に相当な負荷がかかっていたかを申し立ててもらい、しっかり「相当長期間の業務による非災害性腰痛」として労災認定されましたので、概要を報告します。 【鈴木江郎】
鉤手を使い両手や肩で運ぶ作業
この方の変形性腰椎症の原因となった作業を以下に記します。
まず、A社(1976年頃~1982年頃)では、川崎市営埠頭にて米(紙袋30㌔および麻袋60㌔)を貨車から降ろし、倉庫に積んでいく貨車降ろしと山付け作業および倉庫から出荷のためにトラックに積み込む作業でした。紙袋はゴム手袋で両手で抱えて運び、麻袋は鉤手を使い、肩で担いで運んでいました。
他にも、東京築地市場で煮干し(段ボール10㌔)、わかめ(木箱10㌔)、しおから(プラスチックの樽1~5㌔)、シャケ(木箱10㌔)を手運びしました。そして築地市場にトラックや貨車で運ばれてきた上記商品を置き場に運ぶ、競りで購入した業者のターレットトラック(構内運搬自動車)に商品を積み込む作業など行いました。
また、横浜鈴繁埠頭にてビートバルブ(麻袋60㌔)、ヘイキューブ(麻袋45㌔)、古新聞の束(バンドで巻いてある50㌔)を、手鉤を使い倉庫へ積み込む作業を行いました。
艀から倉庫への積み込み作業
次に、B社(1984年頃~1993年頃)では製油倉庫の作業でしたので、扱う商品は綿実油と搾りかすです。まず、艀から倉庫に積み込むまでの作業として、綿実(麻袋40㌔~60㌔)を艀内すれぎ作業(2本の綱で商品を括る)、艀からモッコによる陸揚げ作業、トラックに積み込む作業、倉庫への積み込み作業を行いました。1日当り300㌧の艀1隻半を4人での作業なので1人当り75㌧ですから、麻袋だと毎日1人1875袋~1250袋の作業でした。
また、製油倉庫内では搾った油のカスを紙袋30㌔、麻袋60㌔の解袋切り込み、ホッパーから袋詰め、袋を担いでパレット積み込み(パレ取り)、倉庫に山付け作業を行いました。多い時は3人で100㌧なので、1人当り紙袋30㌔だと1100袋、麻袋60㌔だと550袋の作業でした。
とうもろこし(麻袋100㌔)の艀揚げ作業は、船の中でのパレ取り作業を4人で300㌧、1人当り麻袋100㌔で750袋の作業でした。
フレコンバックのフォークリフト運搬作業
1989年頃からはフレコンバック等をフォークリフトで運ぶ業務を毎日行いました。フォークリフトはTCM(東洋運搬機)2㌧半でしたが、約1㌧半を積んでいました。このフォークリフト運転の振動がとても酷かったのです。まず、フレコンバックを運ぶ際は正面が荷物で見えないので、基本的にバック運転で運ぶので、腰を捻って後ろを見ながら運転します。ハンドルは左手操作が基本なので、右側から後ろを向いて運転していました。腰も右側に負担がかかるので、この方の腰痛も右側が酷いです。フレコンバック以外の荷物の場合は前が見えるので通常の前向き運転でした。
また、坂道に入る時と坂道を降りた時、倉庫の出入口の段差を超える際など、ドンッと壁にぶつかるような振動を腰に受け、腰に相当な負荷がかかっていました。更に、敷地の「でこぼこ」やトレーラーやトラックによる穴など凸凹が酷く、腰に相当な振動がかかりました。運ぶ時間が限られているので、ゆっくり運転はできない状況でした。
白手帳の日雇い時代の作業
1994年頃から1996年頃までは白手帳の日雇いで働きました。現場は川崎三井埠頭、横浜大黒ふ頭、三重県の伊賀上野農協など色々な所で港湾荷役作業に従事しました。この頃は、コーヒー豆(麻袋70~80㌔)、とうもろこし(麻袋100㌔)、ビートバルブ(麻袋60㌔)、大豆(紙袋30㌔、麻袋60㌔)などを手担ぎしていました。
その後、C社(1996年頃~2023年)に入り、大豆(紙袋30㌔、麻袋60㌔)で1日あたり麻袋60㌔の場合150㌧(2500袋)、紙袋30㌔の場合100㌧(約3500袋)を取り扱いました。作業は、袋詰め、パレットへの積み込み、倉庫への積み込み作業で、紙袋はゴム手袋で両手で抱え、麻袋は手鉤を使って運びました。
フォークリフト運転で坂道を上るランディング
C社でも2010年頃からフォークリフト運転を行いました。車種はトヨタの2㌧半(後に3㌧)フォークリフト(ジェネオ)でした。フォークリフトで運ぶ商品は、大豆、フレコンバックでした。倉庫の出入口の段差、でこぼこ敷地、トレーラーやトラックによる穴など凸凹も酷く、ドンッと反動が強く、腰に負荷がかかっていました。運ぶ時間が限られるので、ゆっくり運転はできません。B社でのフォークリフト運転と同様に、フレコンバックは高さがあるのでバックで運転します。大豆は高さがあまりなく、前向き運転です。バック運転では腰を捻って後ろを見ながら運転します。左ハンドルは左が基本なので、右側から後ろを向いて運転していました。前向き運転の際にも、坂道を上る時(コンテナに乗り降りする際の斜路・ランディング作業)、昇りの最初の所でドンッと車体が撥ねて振動が特に酷かったです。そのランディング作業は1日100回以上ありました。
変形性腰椎症を発症 非災害性腰痛で労災認定
これらの腰部に過度な負担がかかる重筋肉作業およびフォークリフト運転により腰椎が変形し、変形性腰椎症を発症されました。主治医である港町診療所の大脇医師、また神奈川労働局の地方労災医員である戸口医師も、腰椎の変形が顕著であり、腰部に過度の負担がかかる作業に長年従事したとして、非災害性腰痛として労災認定しました。